文部科学省は2025年4月25日、「大学等における学修歴証明書のデジタル化の普及及び社会への対応に関する調査研究」報告書を公表しました。
本調査では、国内大学や企業におけるデジタル証明書の導入・受領状況が明らかにされるとともに、普及促進に向けた課題や今後の展望も提示されています。
国内におけるデジタル学修歴証明書の現状と課題、そしてこれからの方向性について詳しく見ていきます。
デジタル学修歴証明書とは? — 国際標準への対応を目指して
学修歴証明書とは、学位記や卒業証明書、成績証明書など、大学や高等教育機関において取得した学びの記録を証明する文書です。
これまでは紙媒体で発行されることが一般的でしたが、世界では近年、これらを電子媒体(主にPDF形式)で発行する「デジタル学修歴証明書」の普及が進んでいます。
特に、電子署名やタイムスタンプを付加することで改ざんリスクを防止し、国際通用性や真正性を確保できる点が大きな特徴です。
文部科学省も、国内大学の国際競争力強化や学び直し需要の拡大に対応するため、デジタル化を推進する方針を明確にしています。
また、教育未来創造会議(政府の有識者会議)による提言でも、「学修歴データのデジタル基盤整備」が強く求められており、大学改革の重要な一環と位置づけられています。
大学における導入状況 — 全体の15%にとどまる現実
文科省の調査によると、デジタル学修歴証明書を発行している、または導入準備中である大学等は、回答した機関のうち約15%にとどまりました。
内訳としては、「発行済み」が約10%、「導入準備中」が約5%となっており、まだ全国的にはごく一部の先進校に限られている状況です。
デジタル化に取り組んでいる理由としては、
- 「在校生の就職活動の利便性向上」(74.6%)
- 「卒業生の転職・海外赴任時の利便性向上」(69.3%)
- 「証明書発行事務の効率化・職員負担軽減」(63.2%)
などが挙げられています。
これにより、学生本人だけでなく、大学側にも業務効率化というメリットが期待されていることがわかります。
一方で、導入に至っていない大学が多数を占めている理由については、
- 「必要なシステム要件や導入モデルの情報が不足している」(56.7%)
- 「予算確保が困難」(56.0%)
といった現実的な課題が浮かび上がっています。
特に地方の中小規模大学では、導入コストの問題が大きなハードルとなっているようです。
技術方式と信頼性確保への工夫
導入している大学の技術方式を見ると、9割以上がPDFベースの発行を採用しており、
その多くに電子署名、タイムスタンプ、パスワード保護などのセキュリティ対策が施されています。
さらに、実際の運用にあたっては、
- サーバー上のデータを最小限にする
- デジタル証明書を大学から直接提出先に送付する運用
- 申請時の提出先情報を証明書に明記し、転用防止を図る
など、改ざんリスクや不正利用防止に向けた対策が講じられています。
また、発行にかかるコストについては、多くの大学が紙媒体と同額の発行手数料を設定しており、収支バランスを取る工夫も進められています。
民間企業側の受け入れ状況 — まだ道半ば
一方、企業側におけるデジタル学修歴証明書の受領状況は、依然として限定的です。
調査によれば、デジタル証明書を「恒常的または部分的に受け入れている」と回答した企業はわずか約17%にとどまっています。
多くの企業は、
- 「紙の原本管理を原則としているため」(65.5%)
- 「特段、デジタル受領の必要性を感じていない」
などの理由で、紙媒体に依存する運用を続けています。
しかし、デジタル証明書受領のメリットも一定程度認識されています。
たとえば、
- 「発行から受領までのリードタイム短縮」(64.8%)
- 「汚損リスクの低減」(38.3%)
- 「リモートワーク対応」(32.8%)
などが挙げられており、今後企業側の意識改革が進めば、受け入れが拡大する可能性もあります。
海外との比較 — 世界標準との差をどう埋めるか?
世界に目を向けると、英国の「UK Biobank」や、米国の「All of Us」など、バイオバンクを含めたデジタル学修歴管理は急速に進展しています。
デジタル証明書の発行と流通は、国際的な人材移動や生涯学習支援のインフラとして欠かせないものになりつつあります。
日本でも、海外留学や国際的なキャリア形成を希望する学生にとって、デジタル学修歴証明書の整備は不可欠です。
その意味でも、国内の大学や企業がより迅速に対応を進めることが求められています。
引用元:
文部科学省「大学等における学修歴証明書のデジタル化の普及及び社会への対応に関する調査研究」報告書(令和7年3月)


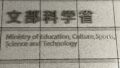
コメント