2025年4月25日、文部科学省においてあべ文部科学大臣による定例記者会見が行われました。会見では公立高校入試制度の改革やロケット打ち上げ計画、福島第一原発の廃炉に向けた取り組みなど、多岐にわたる政策について説明がありました。特に注目を集めたのは、政府のデジタル改革会議で指示された公立高校入試のデジタル化と「単願制」の見直しについての言及です。
公立高校入試、デジタル化と複願制導入へ検討開始
あべ文科相は、4月22日に開催されたデジタル行政・規制・財政改革会議について言及。会議では公立高校入試において「1人の生徒が1つの公立高校にしか願書を出せない、いわゆる単願制」の課題とその解消策が議論され、石倉平デジタル担当大臣とともに「生徒の希望する進学につながることのメリット、また現場の課題を丁寧に考慮し、希望する自治体での事例創出の具体化を図るよう」総理から指示があったと説明しました。
現在、多くの都道府県では一人の生徒が出願できる公立高校を一校に限定する「単願制」を採用しています。この制度は合格者の確実な入学を見込めるメリットがある一方、受験生の選択肢が狭まるとの指摘もあります。
あべ文科相は「デジタル技術を活用した複願制についてもメリットが考えられる一方で、生徒の多様な個性と能力が十分に評価されるか、学校の特色・魅力が損なわれないか、地域人材を育成する機能に影響がないかなどの課題も想定される」と述べました。
文科省としては「メリットや課題について整理をしつつ、高校教育の向上につながるよう、自治体・高校関係者の意見もよく伺い、関係省庁とも十分に連携の上、丁寧に検討していく」との姿勢を示しています。
H2Aロケット最終号機、6月24日に打ち上げへ
科学技術行政の面では、あべ文科相はJAXAが公表するH2Aロケット55号機について報告。このロケットは温室効果ガス・水循環観測技術衛星「GOSAT-GW」を搭載し、6月24日に打ち上げを予定していることを明らかにしました。
「GOSAT-GW」はJAXAと環境省が共同で開発した衛星で、温室効果ガス濃度や海面水温等の高度な測定が可能となります。あべ文科相は「気候変動や水産などの幅広い分野において貢献することを期待している」と述べました。
また、H2Aロケットはこの55号機で最終号機を迎えることになります。2001年からの運用期間において、打ち上げを実施した49機中48機が成功するという世界最高水準の成功率を誇ってきました。あべ文科相は「国内外官民の多様な衛星を打ち上げ、国民の皆様に親しまれるとともに、地球上の様々な課題の解決、より豊かな経済社会活動の実現に着実に貢献してきた」と評価しています。
H2Aロケットの技術はすでに後継のH3ロケットの開発・運用に引き継がれており、「今後次期の基幹ロケットに向けた検討においても重要な知見として活用される」と説明。文科省としては「我が国の自立性確保と国際競争力強化のための重要な基幹ロケットの開発・運用を引き続き着実に進めていきたい」との方針を示しました。
少子時代の地域大学振興—学生を含む有識者会議で議論
高等教育政策については、4月21日に開催された「少子時代の地域大学振興に関する有識者会議」に大学院生6人が委員として参加したことについて言及。あべ文科相は「本有識者会議においては、本年2月の中央教育審議会の答申を踏まえ、地域の高等教育への接続確保、また地方創生などの地域の大学振興のあり方について総合的に議論するもの」と説明しました。
「学生を含め、産学官金労言から幅広く参画いただくとともに、地域大学振興に関連する関係省庁にもオブザーバー参加を依頼している」と述べ、特に学生の委員に対しては「地域の高等教育機関がどのような場であるべきなのか、また大学・地方公共団体・産業界等に期待することなどを率直にお話しいただきたい」と期待を表明しました。
文科省としても「この有識者会議における議論を踏まえながら、関係省庁とも連携を図りながら、各地域における大学振興の取り組みに関する検討を進めていきたい」との考えを示しています。
インターナショナルスクールに通う日本国籍の子どもの義務教育問題
基礎教育政策に関しては、NHKの記者から、東京23区で一条校(学校教育法第1条に定められた正規の学校)に通わずインターナショナルスクールに通う日本国籍の子どもが少なくとも4800人いるという報道についての見解を問われました。
あべ文科相は「義務教育は憲法に規定する教育を受ける権利を保障するものであり、学校教育法においては保護者にその子女を小学校・中学校等に修学させる義務を課している」と前置きした上で、市町村教育委員会は「保護者がこの修学義務を履行していると認められる時は、保護者に対して児童生徒の出席を督促している」と説明しました。
一方で「例えば帰国児童生徒の日本語能力が養われるまでの一定の期間、適切な期間で日本語の教育を受ける等の措置が講じられている場合など、市町村教育委員会から修学義務の猶予または免除を受けてインターナショナルスクールに通学している場合もあり、個別の事情に応じた判断が子どもの利益につながる」との見解を示しました。
「こうした制度を踏まえて、各市町村教育委員会において適切に対応していくべきものと考えており、文部科学省として現時点で調査を行うことは考えていない」と述べ、国としての一律の対応には消極的な姿勢を示しました。
その他の重要課題:山林火災研究と福島第一原発廃炉
会見では、このほか岩手県大船渡市で発生した大規模な山林火災について、「今後の防災対策に生かすため、火災の自然要因の解明等に向けた調査研究を実施する」と発表。東京理科大学火災科学研究所の桑名和典教授を研究代表者とする研究に対し、科学研究費助成事業の「特別研究促進費」により助成することを決定したことを明らかにしました。
また、4月23日に東京電力が発表した福島第一原子力発電所2号機における2回目の燃料デブリの試験的取り出し完了についても報告。今回取り出された燃料デブリは、経済産業省の補助事業において日本原子力研究開発機構(JAEA)が分析を実施する予定で、「JAEAが燃料デブリの分析を通じて今後の燃料デブリ取り出しの方策検討のために貢献することにより、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉に向けた取り組みが進展することを期待している」と語りました。
引用元:

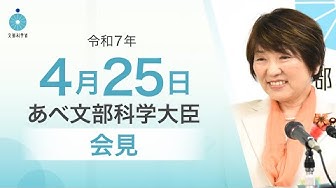

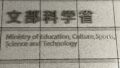
コメント